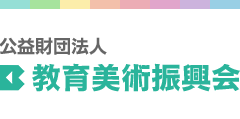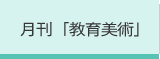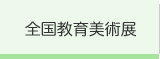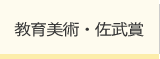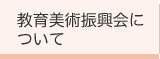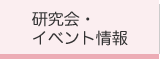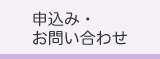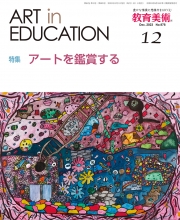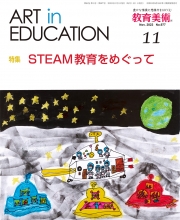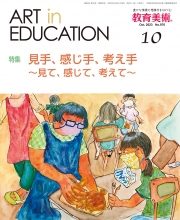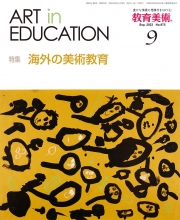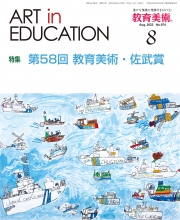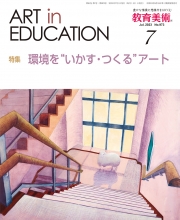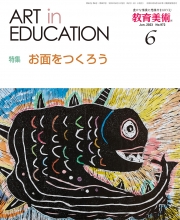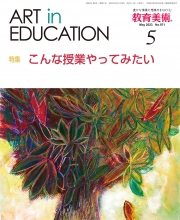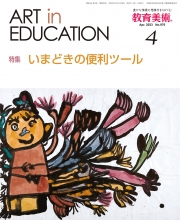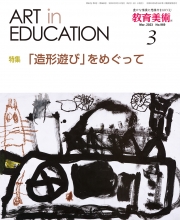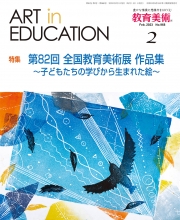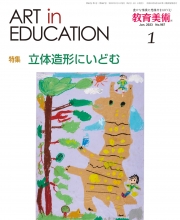月刊「教育美術」
月刊誌『教育美術』は、1935年創刊より日本における美術教育の進歩と振興を目指しています。教育現場の優れた実践や研究を紹介しながら、造形・美術教育の理念を広め、子どもたちが豊かな情操と創造力を育むことができるよう、また指導者が実践をより深めることができるように独自の情報発信に努めています。
美術教育の授業実践レポート、造形・美術教育のトレンドをはじめ幅広い情報を網羅。全国の幼稚園や保育所、小学校、中学校など、造形・美術教育に携わる人々のニーズに合わせた情報を提供する専門誌です。造形・美術教育の貴重な資料として全国の教育委員会、大学の研究室などから購読されているほか、全国の大学図書館などに所蔵され、指導者だけでなく研究者にも幅広く活用されています。