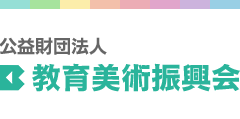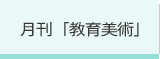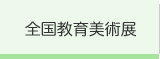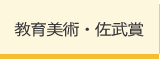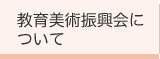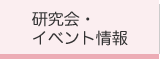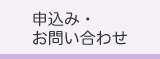教育美術・佐武賞について
「教育美術・佐武賞」は、公益財団法人教育美術振興会(当時:財団法人教育美術振興会)の初代理事長として、長い年月ひたすら美術教育の振興に心をくだき、生涯をかけて大きな力を尽くされた佐武林蔵先生(昭和43 年没)のご寄付によって、昭和41(1966)年に設立されました。
現場の先生方の実践に光をあてることにより、子供と共につくりあげた優れた授業を広め、指導者の育成と、図画工作・美術科教育の発展に貢献することが本賞の狙いです。そして現場の先生方が日々の実践の悩みから見出した課題や、新学習指導要領の中から見つけた課題などを解決するために、どのような実践をしているかを大事にしています。
本賞が契機となって、学校現場における実践活動が活性化し、研究の輪が一層広がることを願っています。
※佐武賞について動画による説明 → https://www.youtube.com/watch?v=8VFZLkljq5Q
□教育美術チャンネル(Youtube) → https://www.youtube.com/watch?v=LCLGYEsE6vY